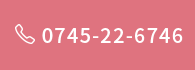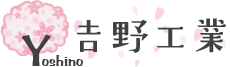冬至とは1年で1番、太陽の出ている時間が短く、夜が長い日です。
冬至がいつかは天文学的に決まり、毎年、12月21日か22日です。
2021年の冬至は、12月22日(水)。
冬至に食べる食べ物って…かぼちゃだっけ?どうして柚子湯に入るの?
そんな冬至の食べ物や風習などを調べてみました。
冬至の食べ物「かぼちゃ」
冬至の食べ物といえばかぼちゃ。
ところで、なぜ冬至にはかぼちゃなのでしょう?
かぼちゃの原産地は中南米。もともと暑い国の野菜なので、かぼちゃは夏から秋に収穫されます。
ただ、カットさえしなければ、風通しのいい涼しい場所で2~3カ月保存することが可能です。
かぼちゃは、体内でビタミンAに変わるカロテンや、ビタミンB1、B2、C、E、
食物繊維をたっぷり含んだ緑黄色野菜。
新鮮な野菜が少なくなる時期、これからの冬を乗り切るためにも、
冬至という節目の日にかぼちゃを味わって栄養をつけよう…という先人の知恵なのです。
ただ、江戸時代の文献には「冬至にかぼちゃ」という内容の記述はなく、
明治以降に生まれた比較的新しい習慣と考えられています。
冬至の風習「柚子湯」
もう一つの冬至の風習が柚子湯(ゆずゆ)。この習慣は江戸時代からあったようです。
1838(天保9)年に刊行された、江戸の年中行事を紹介する「東都歳事記(とうとさいじき)」によると、
「冬至 今日銭湯風呂屋にて柚湯を焚く」との記述があります。
「冬至」を「湯治」にかけ、「柚子」を「融通が利く」(=体が丈夫)にかけて、
お風呂屋さんが始めたとされています。
江戸っ子ならではのしゃれたイベントですね。
柚子はちょうど11月~12月が収穫期。
柚子の果皮には、風邪予防や保湿にいいとされるビタミンCや、
血行改善を促すといわれるヘスペリジン(フラボノイド)などが豊富に含まれています。
昔の人は、旬の柚子が健康にいいことを経験的に知っていたのでしょうね。
まとめ
冬至が過ぎれば、少しずつ日が長くなっていきます。とはいえ、寒さはこれからが本番。
ホックホクのかぼちゃとあったかい柚子湯で、冬を乗り切りましょう!