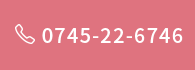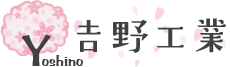梅雨とは、5月から7月にかけて曇りや雨が多くなる雨季のことを指します。
梅雨の始まりは「梅雨入り」、梅雨の終わりは「梅雨明け」と呼ばれ、地域によって時期は異なりますが、
一般的に日本では6月が梅雨の時期としてメジャーですね。
雨の印象が強い「梅雨」
なぜ「梅」という漢字が使われているのでしょうか?
梅雨に「梅」の漢字が使われる由来
「梅雨」は、中国から日本へ伝わってきた言葉だと言われています。
「梅雨」と書くようになった理由は様々あるようですが、一説によると、
雨が降る季節はカビが生えやすいため、黴(かび)という漢字を使って「黴雨(つゆ)」と呼ばれていたものの、
漢字が読みづらいために「梅雨」という漢字に変化したとされています。
他にも、中国で梅の実が熟す時期が雨期であったため、
「梅」という漢字を使うようになったという言い伝えもあるようです。
日本で「梅雨(つゆ)」と呼ばれるようになった理由
「ばいう」と「つゆ」、読み方が2つあるのは、ややこしいですね。どうして2つあるのでしょうか。
元々は「ばいう」として中国から伝わり、江戸時代に「つゆ」という発音が生まれたようです。
「つゆ」と呼ぶようになったのにはいくつか理由があるようですが、
一つは、雨が降って枝先や葉っぱについた「露(つゆ)」を連想したことがきっかけと伝えられています。
また、クリ(栗)の花から「つゆ」という呼び方が生まれた説もあります。
クリの花が落ちることを栗花落(つゆり)と呼びます。
栗の花が落ちる時期と梅雨入りの時期が重なるので、そこから「つゆ」という言い方が生まれた、という説です。
さらに雨が降ることで梅の実が潰れて落ちるため、
「潰ゆ(ついゆ)」と言われるうちに「つゆ」という呼び名に変化した説など、
明確に定められているものはないようです。
多くの人にとって、梅雨は一番嫌いな季節かもしれません。
しかし、梅雨に雨が降れば夏の水不足が防げるので、野菜や米などの植物も元気に育ちます。
梅雨を理解して、楽しく過ごしてみるのもいいかもしれませんね。
奈良を中心に近畿での防水・断熱工事は吉野工業にお任せ下さい。
会社名:吉野工業
住所:〒635-0055 奈良県大和高田市曽大根2-9-4
TEL:0745-22-6746
業務内容:発泡ウレタン吹付け、耐火被覆吹付、GL工事、防水工事、塗装工事